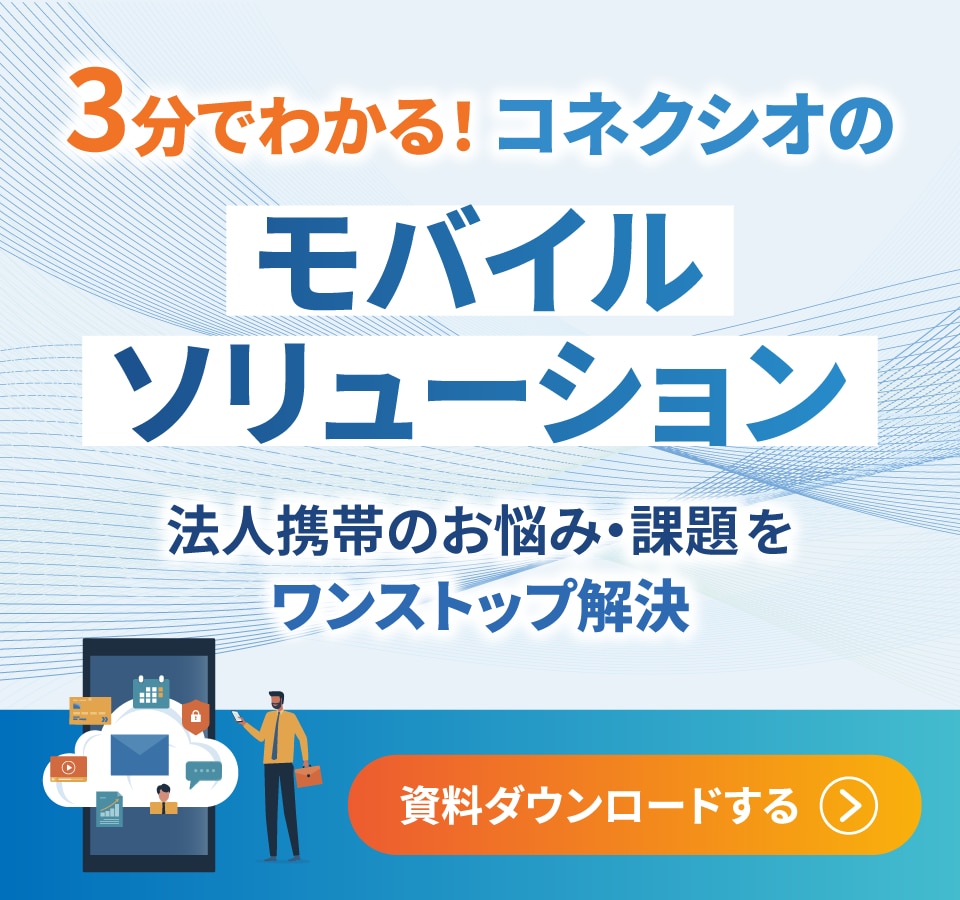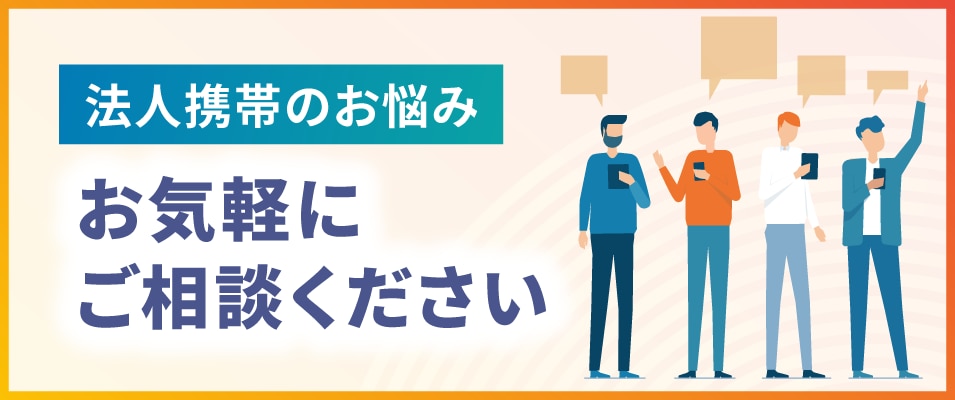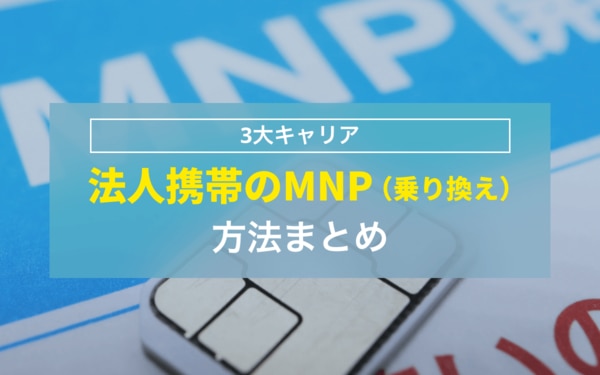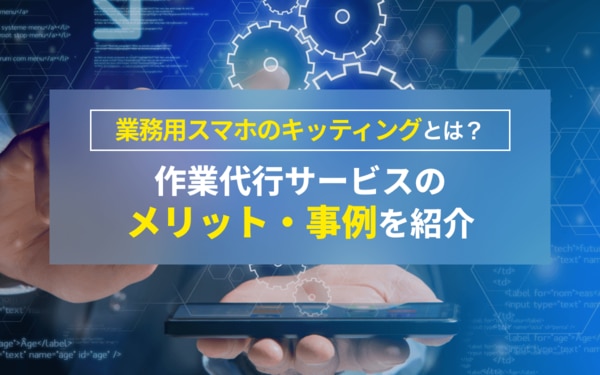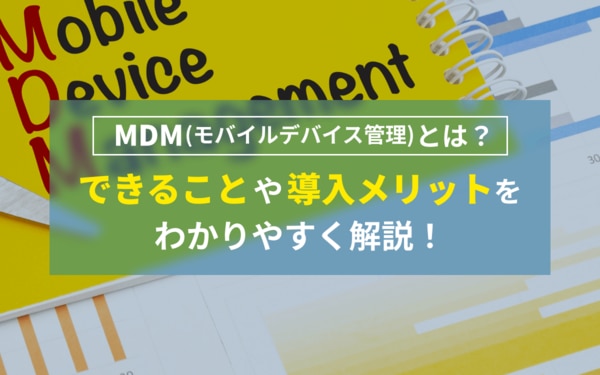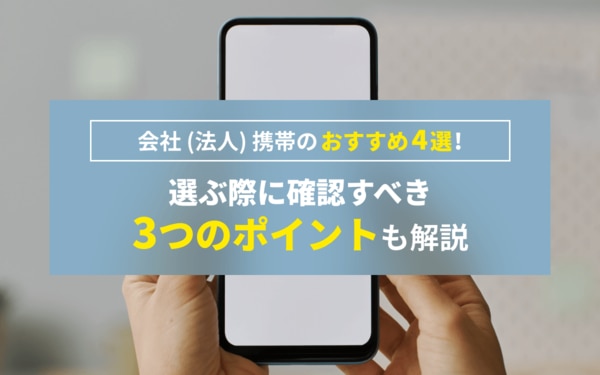ヘルプデスク運用とは?業務を効率化するコツも徹底解説!
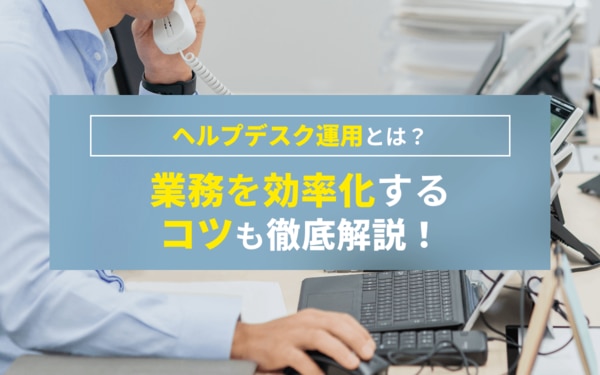
ヘルプデスクの継続的維持や業務負荷についてお悩みではありませんか?
ヘルプデスクは、問い合わせ対応やトラブル解決を担う重要な業務です。
しかし、業務量は膨大であり、稼働逼迫を起こしやすい、体制維持が難しいことが課題としてあげられます。
継続的な運用体制と業務稼働を分散させ、効率的な対応を実現することが大切です。
今回は、ヘルプデスク運用の概要や課題、効率化の方法について解説します。
ヘルプデスク運用にお悩みの方は、本記事の内容をお役立てください。
目次[非表示]
ヘルプデスクの運用とは

ヘルプデスク運用とは、社内外からの問い合わせに対応し、問題解決をサポートする業務を担います。また、トラブル発生時の再発防止策対応も行います。
問い合わせ対応を受けるだけではなく、蓄積されたノウハウから対応力の向上にもつなげていきます。
ヘルプデスクがあることで、スムーズな問題解決につながり、お客様や従業員の満足度向上を促す役割ともなります。
ただし、規模や人員構成、直面する課題は企業ごとに異なるため、運用体制は状況に応じて柔軟に設計することが必要です。
社内向け・顧客向けヘルプデスクの違い
社内向けヘルプデスクは、社員からの問い合わせ対応をメインとし、業務システムやIT機器に関するサポートを行います。
一方、顧客からの製品やサービスに関する問い合わせ対応を行うのは、顧客向けヘルプデスクです。
ここからは、それぞれの違いについて解説します。
社内向けヘルプデスク
社内向けヘルプデスクは、社員が利用するシステムや端末に関するトラブルを解決し、スムーズな業務進行を可能にします。
パソコンやソフトウェアの不具合対応、ネットワーク接続の問題解消、操作方法の指導などが社内向けヘルプデスクの業務です。
これにより、従業員が抱える作業上のストレスを軽減し、生産性向上につなげられます。
顧客向けのヘルプデスクとは異なり、社内の従業員を対象としている点が特徴です。
顧客向けヘルプデスク
顧客向けヘルプデスクは、主に製品やサービスに関する質問やトラブルに対応する窓口です。
操作方法の説明や不具合の解消が業務内容に含まれ、顧客の満足度向上につながる業務です。
顧客対応スキルを求められる点が特徴で、企業の信頼度を高める役割も果たします。
ヘルプデスクとシステム運用保守の違い
ヘルプデスクとシステム運用保守は、役割が異なる業務です。
ヘルプデスクは、利用中のシステムに関する問い合わせ対応を担当します。
利用者から寄せられる操作方法やトラブルの相談を受け付け、必要に応じて専門部署に引き継ぎます。
一方、システム運用保守は、システムの安定稼働を目的とした業務です。
主にシステムの監視や障害発生時の対応を行い、システムの開発関連の問題解消にも携わります。
ヘルプデスクは直接利用者と接点を持つ一方で、運用保守は利用者対応を行わず、裏方としてサポートするイメージです。
両者の連携がシステム全体の効率化と安定性を支えます。
■合わせて読みたい資料
ヘルプデスク運用のメリット
ヘルプデスクを運用すると、以下のようなメリットがあります。
- 業務の停滞を防ぐ
- ノウハウが蓄積できる
- 顧客満足度が高まる
ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
業務の停滞を防ぐ
社内向けのヘルプデスクでは、社内で発生するシステムトラブルや操作の不明点に迅速に対応することで、業務の停滞を防ぐことができます。
また、対応履歴を蓄積・活用することで、同様のトラブルが発生した際にもスムーズな対応が期待できます。
問題解決までの時間が短縮されるため、社員が本来の業務に集中できます。
ノウハウが蓄積できる
ヘルプデスク運用では、問い合わせを集約することで、トラブル解決のノウハウが蓄積されます。
過去の不具合対応や問い合わせ傾向、イレギュラーな要望を記録することで、同様の問い合わせに対して迅速な対応することが可能です。
蓄積した情報は、業務フローの見直しや対応の質向上にもつながります。
顧客満足度が高まる
ヘルプデスクの導入は、顧客の満足度を高める要素となります。
製品やサービスに関する問い合わせに対して、適切なサポートを提供することで、顧客の不安を解消し企業への信頼向上にもつながります。
さらに、問い合わせ対応を通じて顧客の声を日常的に集められるため、市場調査にかかる手間や費用をおさえることが可能です。
現場で役立つ情報を効率よく収集することで、業務改善にもつなげられるでしょう。
ヘルプデスク運用の基本構造

ヘルプデスクは主に以下の3要素で構成されています。
- 運用体制
- 運用設計
- 運用管理
それぞれの詳細について、詳しく見ていきましょう。
運用体制
ヘルプデスクの運用体制は、業務が安定的に稼働し続けるためのものです。
運用体制を維持するには、適切なリソースと予算の確保が求められます。
通常時は監視を中心に、必要なときに対応する体制が効率的です。
人手が足りないときは外部委託も視野に入れるとよいでしょう。
さらに、非常時に備えた継続計画や再発防止の仕組みを整えることで、安定した運用と信頼の維持につながります。
運用設計
ヘルプデスクを安定的に運用するには、運用設計をしっかり行うことが重要です。
このとき、運用設計が明確になっていないと、問題発生時に速やかな対応を行うことができなくなります。
運用設計は3W1H(誰が、何を、いつ、どう動くのか)を軸として具体化することが重要です。
一連の業務の流れを見渡せる設計を整えることで、対応ミスの防止と業務負担の偏りを軽減できます。
また、業務を洗い出す際は、定期業務とイレギュラーで発生する業務を分けて整理しましょう。
運用管理
ヘルプデスクの運用管理とは、業務全体を把握し、改善につなげる取り組みを指します。
蓄積した対応履歴をもとに、よくある質問や操作ミスを分析すれば、FAQやマニュアルの精度も高まるでしょう。
マニュアルや操作ガイドなど常に更新し、展開することで、お問い合わせ対応件数の工数削減などにつながる可能性があります。
また、使い方の案内や注意点を発信すれば、システム利用者の負担も軽くなります。
トラブルの予防や負荷の分散を目指すには、積極的な情報整理と継続的な見直しが必要です。
運用管理は、業務の維持だけでなく、継続的な改善を視野に入れることが求められます。
ヘルプデスク運用の課題
ヘルプデスク運用にはいくつかの課題があります。
- 問い合わせの集中による対応遅延
- 対応範囲が広い
ここからは、ヘルプデスク運用の課題について見ていきましょう。
問い合わせの集中による対応遅延
ヘルプデスクへの問い合わせが一時的に集中すると、対応が追いつかなくなり、遅延が発生しやすくなります。
件数の増加や内容の複雑化によって、対応時間が長引き、業務全体に負荷がかかる可能性も考えられるでしょう。
こうした状況を防ぐには、よくある質問を整理し、マニュアルやFAQで自己解決を促す仕組みづくりが有効です。
業務を圧迫する前に、対応を分担しやすい流れと、対応フローを整えておく必要があります。
問い合わせが集中したときを見越して、事前に準備しておく体制づくりが大切です。
対応範囲が広い
ヘルプデスクの業務は、社内外の多様なシステムに関わるため、対応範囲が広がりやすい傾向にあります。
また、幅広いIT知識が必要で、部門ごとの利用環境や端末の違いに加えて、クラウドや専用ツールの増加によって、求められる知識も複雑になりがちです。
また、企業が成長すればシステム数も増え、さらに支援範囲が広がる可能性があります。
このとき、パソコンの設定やネットワーク接続など、ヘルプデスクの対応範囲は多岐にわたるでしょう。
担当者は、日々のトラブル対応に加え、新しい機能や更新情報の習得も欠かせません。
技術の変化に追いつくには、研修や情報共有の仕組みを整えておく必要があります。
想定外の質問にも対応できるよう、柔軟な運用体制を整備することが重要です。
属人化(特定の担当者しか把握できていない)を防ぎながら、知識を積み重ねる工夫が、安定した運用につながります。
ヘルプデスク運用を効率的に行う方法

ヘルプデスクの効率化は、利用者満足度を高め、担当者の負担を軽減します。
- 業務範囲を明確化する
- 担当者のスキルを向上させる
- マニュアルを整備する
- ITツールを活用する
ここでは、ヘルプデスク運用を効率的に行う方法についてまとめました。
業務範囲を明確化する
ヘルプデスクを効率よく運用するには、業務範囲の明確化が重要なポイントです。
担当する業務の範囲が曖昧なままだと、対応の重複や抜け漏れが起きやすくなります。
あらかじめ対応可能な範囲や判断基準を定めておけば、引き継ぎや優先順位の判断にも迷いません。
業務の分担が明確になることで、担当者それぞれが自分の役割を把握しやすくなります。
業務範囲を決める際は、負荷が偏らないよう業務量を均等に調整する工夫も必要です。
管理の仕組みを整えれば、全体の流れが可視化され、効率的な運用と負担軽減を実現できるでしょう。
担当者のスキルを向上させる
ヘルプデスクの効率を高めるには、担当者のスキル強化が必要です。
ITの基礎知識や対応力が不足していると、解決に時間がかかり、問い合わせ対応が滞りがちになります。
ロールプレイングや定期研修を行うことで、実践的な判断力を養うことができるでしょう。
また、過去の対応事例やFAQをチームで共有すれば、属人化を防ぎ、全体の対応力を底上げできます。
さらに、よくある質問をまとめた資料や操作ガイドを整備すれば、利用者自身が解決できる環境も整えられるでしょう。
マニュアルを整備する
ヘルプデスクを効率よく運用するには、業務内容に即したマニュアルを整備しましょう。
対応の流れや対応例を記載すれば、対応の基準が明確になり、判断の統一が図れます。
マニュアルを整備することで、新任者への業務の引き継ぎもスムーズになり、応対品質を一定に保てるでしょう。
社内向けの案内資料としても活用すれば、問い合わせの削減にもつなげられます。
利用者自身で解決できれば、担当者の負担は軽くなるでしょう。
業務の変化に合わせて内容を更新し、実用性の高いマニュアルを整備することが大切です。
ITツールを活用する
ヘルプデスク業務を効率化するには、目的に合ったITツールの活用が効果的です。
FAQシステムやチャットボットを導入すれば、よくある質問への対応を自動化でき、担当者の負担を軽減できます。
さらに、問い合わせの進捗や対応履歴を一元管理する仕組みを整えれば、対応の重複や漏れも防ぎやすくなるでしょう。
同じ内容の問い合わせが発生した場合でも、過去の対応例をすぐに確認できるため、処理のスピードと正確性が向上します。
ITツールの導入は作業時間の短縮だけでなく、品質の安定にもつながる重要な取り組みです。
運用の手間を減らし、全体の流れを円滑にするための対策として検討しましょう。
ヘルプデスク運用に役立つITツール
ITツールを活用することで、ヘルプデスクの業務を効率化できます。
- 問い合わせ管理システム
- FAQシステム
- チャットボット
それぞれの特徴を把握して、状況に合わせたツールの導入を検討しましょう。
問い合わせ管理システム
問い合わせ管理システムとは、顧客対応に関する情報を一元で管理・共有できるシステムです。
このシステムを導入すれば、過去の対応履歴や顧客データをすぐに確認できるため、対応スピードと正確性が向上します。
タスクごとの進捗を可視化する機能もあるため、業務の偏りや対応漏れを防ぎやすくなります。
担当者が異動や休職で不在になっても、過去の対応内容を共有できるため、引き継ぎもスムーズに進むでしょう。
さらに、蓄積されたデータを分析すれば、業務改善のヒントも得やすくなります。
個々の対応を記録に残すだけでなく、現場全体のパフォーマンス向上にもつながるシステムといえるでしょう。
FAQシステム
FAQシステムとは、よくある質問と回答をまとめて検索できるシステムです。
利用者が自ら情報を探せるため、問い合わせ件数を大幅に減らせます。
キーワード検索やカテゴリ別の分類によって、必要な情報を効率的に見つけられるでしょう。
業務担当者は同じ内容の対応を繰り返す手間が省けるため、本来の業務に集中しやすくなります。
さらに、問い合わせの傾向を分析することで、情報の更新や構成の見直しにも活かせます。
情報が体系化されていれば、社内のマニュアルや対応履歴を検索できる仕組みとしても活用できるでしょう。
チャットボット
チャットボットとは、問い合わせにチャット形式で自動応答する仕組みを指します。
人の手を介さず、24時間対応できるため、利用者は時間を選ばず問題を解決することが可能です。
繰り返しの問い合わせが多い現場では、学習型チャットボットを導入すれば、対応速度が向上し、ヘルプデスクの負担を軽減できます。
初期対応を自動化すれば、担当者は複雑な案件に集中でき、全体の業務効率も上がります。
待ち時間が減ることで顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
ヘルプデスク運用は問い合わせ対応の仕組みを整える業務
今回はヘルプデスク運用について解説しました。
ヘルプデスク運用は、顧客や従業員の問い合わせ対応を効率化することで、業務の円滑化や利用者の満足度向上を実現する取り組みです。
適切な体制構築やITツールの活用により、負担を軽減しつつ高品質な対応が可能となります。
コネクシオ株式会社のマネージドモバイルサービスは、ヘルプデスク運用の業務負担軽減に役立ちます。
スマートフォンの管理業務を一括して委託できるため、スマートフォンに関わる問い合わせ対応が軽減し、それぞれの担当業務に集中できるでしょう。
業務効率化のためにも導入を検討してみてはいかがでしょうか。
■関連サービス:マネージドモバイルサービス
■合わせて読みたい資料