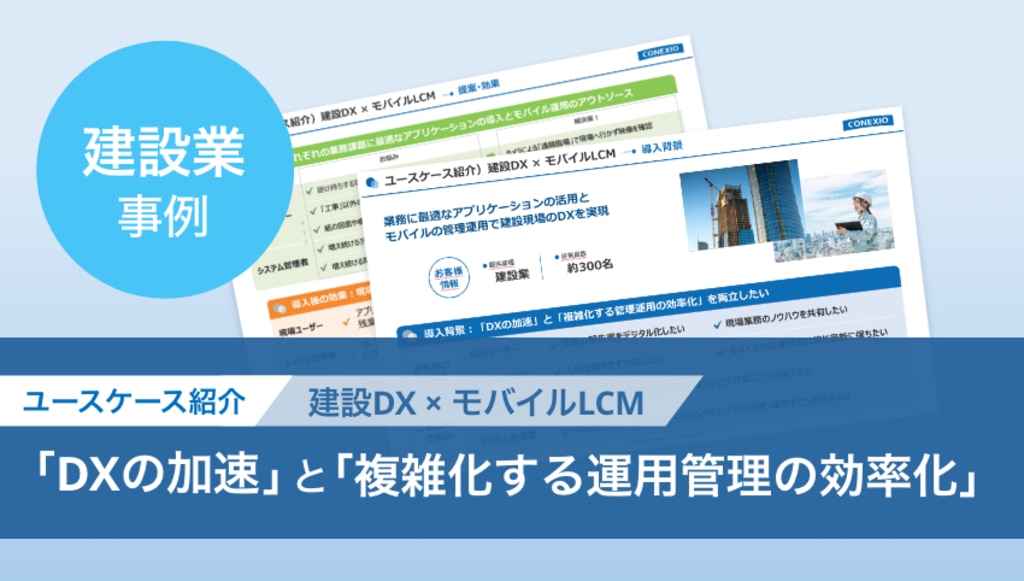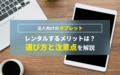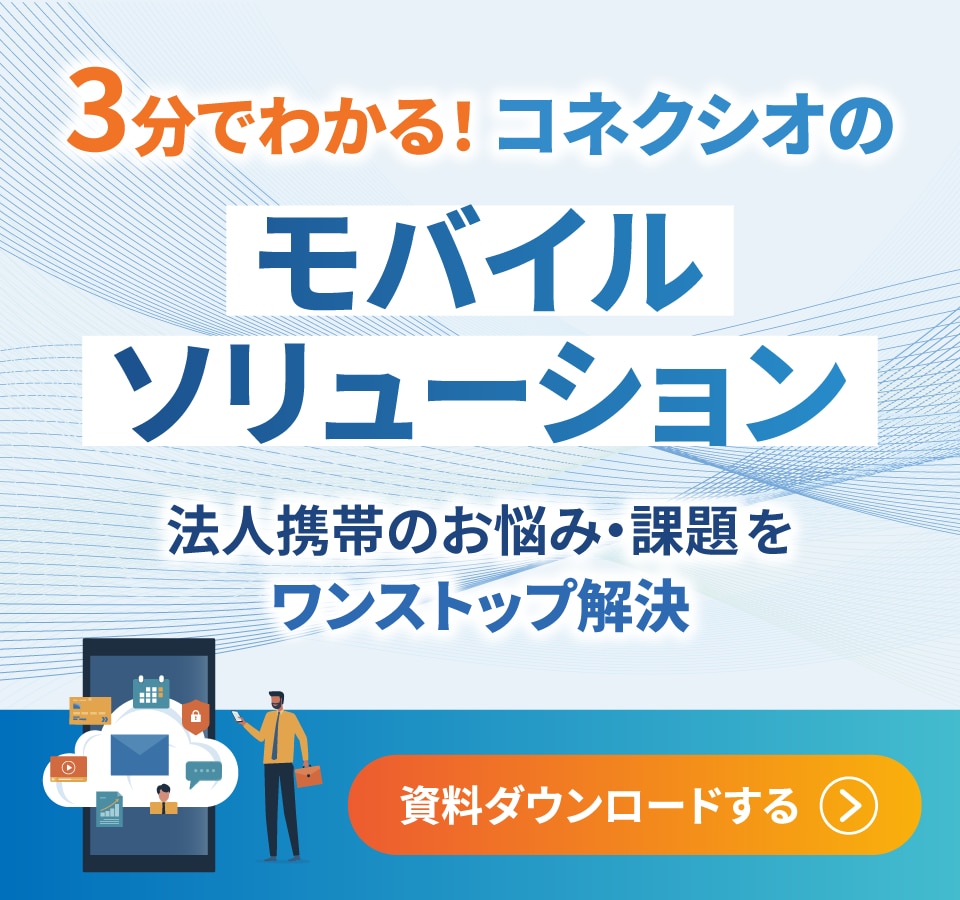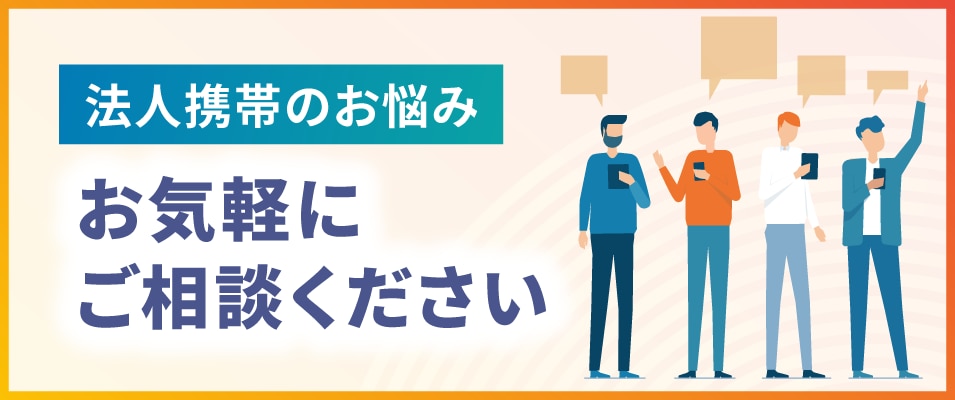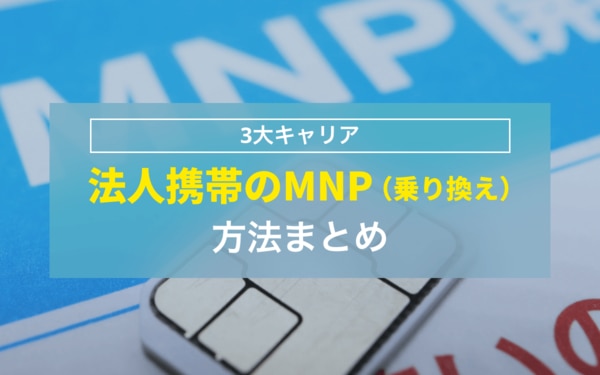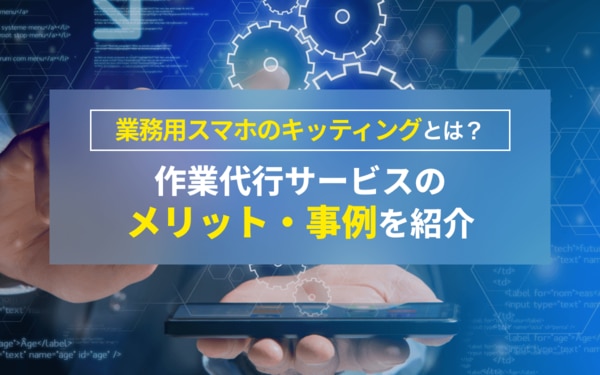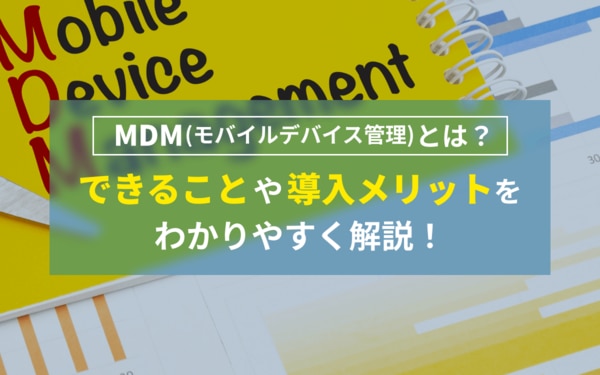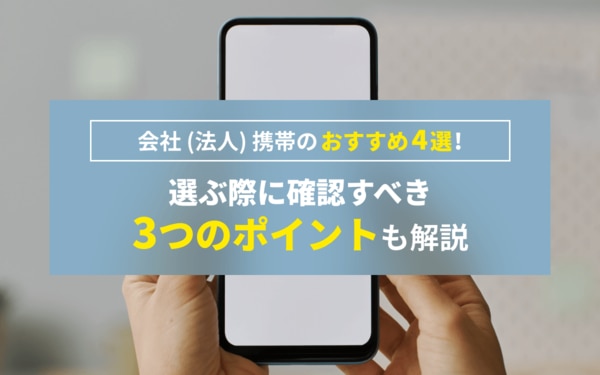病院の業務にタブレットは導入すべき?活用例やメリット・デメリットを解説
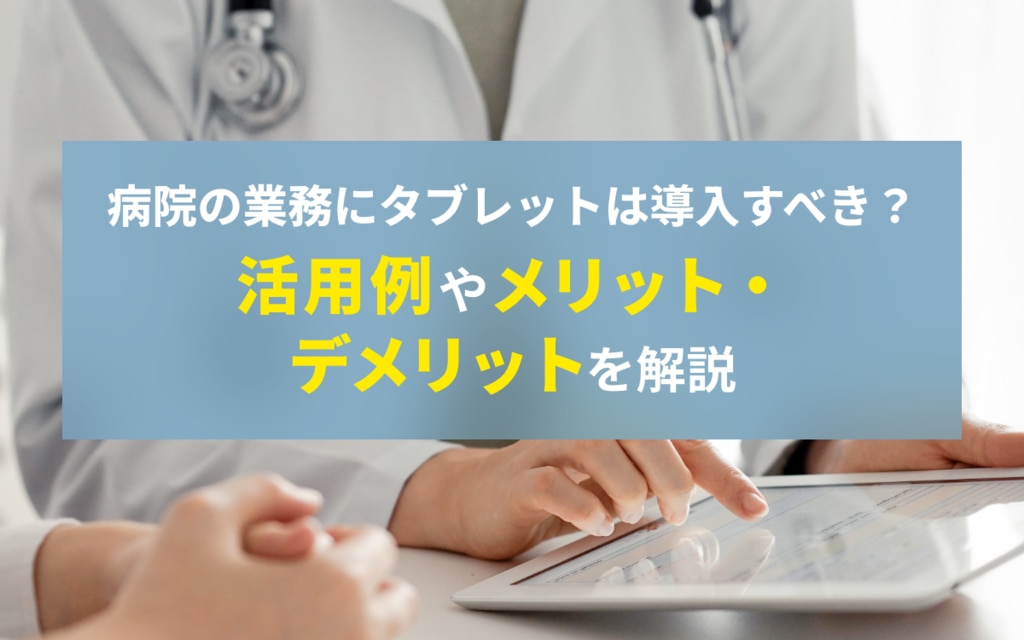
医療現場における業務効率化や患者の満足度向上は、多くの病院が抱える課題です。
紙のカルテや伝票による情報伝達の遅れ、長い待ち時間による患者からのクレームなど、日々の業務に追われることもあるのではないでしょうか。
このような課題の解決策として「タブレット」の活用が注目されています。
本記事では病院におけるタブレットの活用事例や導入のメリット・デメリット、導入に関する注意点を解説します。
実際の活用法を把握し、タブレットを導入すべきかどうかの判断にお役立てください。
病院でタブレットを導入するメリット

病院でのタブレット導入は、業務効率の向上につながり、医療現場の生産性を高める手段であるといえます。
ここでは3つのメリットをまとめました。
情報共有がスムーズになる
病院の規模が大きくなるほど、院内での情報共有や連携のスピードが重要です。
タブレットを電子カルテや問診票として活用することで、患者の情報や検査結果への即時アクセスができます。
診察中に情報をすぐに確認・記録できるため、迅速な処置が可能になります。
緊急時であってもタブレットから状況を送信すれば、リアルタイムの情報が確認できるのもメリットです。
ペーパーレス化の推進
タブレットを活用することで、ペーパーレス化の推進にも貢献できます。
問診票や同意書などの書類をデジタル化することで、情報の検索や共有が容易になり、書類管理の手間を減らすことが可能です。
持ち運びがしやすい
電子カルテがタブレットに保存されていれば遠隔地からでも確認できるため、的確な処置が行え、ミスの削減にもつながります。
タブレットによってはパソコンに近い機能を備えているものもあるため、リハビリ現場など、パソコンでの操作や入力が難しい場面でも有効活用できるでしょう。
なお、携帯性を重視する看護師には小型モデル、画像確認などを行う医師には大型モデルといったように、職種や用途に応じて端末サイズを使い分けることで、より業務効率を高められます。
病院でタブレットを導入するデメリット
メリットだけを考慮してタブレットの導入を決めてしまうと、想定外の問題が発生するかもしれません。
デメリットをしっかりと理解したうえで、導入を検討しましょう。
情報の入力がしづらい場面がある
タッチ操作が基本のタブレットは、看護記録といった長文の入力には不向きな場合があります。
対策として、外付けキーボードに対応したモデルを選ぶなど、端末の拡張性も考慮することが重要です。
システム導入に手間がかかる
タブレットやシステムの導入には、手間がかかります。
導入するものによっては専門的な知識が必要となり、設定が難しいかもしれません。
こうした課題に対しては、専門の導入支援サービスを利用するのも一つの方法です。別途費用は発生しますが、設定ミスを防ぎ、目的や環境に応じた最適な運用が実現できるといったメリットがあります。
ほかにもシンプルなシステムを導入する対策方法もあるため、適した方法を選択するようにしましょう。
紛失時のセキュリティ対策が必要
タブレットでカルテなどを管理する際は、故障や紛失には細心の注意が必要です。
万が一端末を紛失した場合は、タブレット内の情報が漏えいしてしまう可能性もあるでしょう。
導入時にはセキュリティ対策の検討が重要です。
対策方法を明確にしておかなければ、重大なトラブルにつながりかねません。
紛失に関するセキュリティ対策への課題を感じている場合は「MDM」の利用を検討してみましょう。
MDMは「業務用モバイル端末を一元管理するシステム」で、運用代行を提供するサービスもあります。
タブレットだけでなくスマートフォンなどの一元管理も可能です。運用面の課題を感じているのであれば、有効な選択肢といえるでしょう。
病院でのタブレット活用事例8選

タブレットは、病院をはじめとする医療現場でも活用されています。
ここでは、実際の活用シーンを8つの具体的な事例に沿ってご紹介します。
なお、病院でタブレットを活用する際は、多くの場合、電子カルテシステムや専用アプリケーションとの連携が前提となります。タブレット端末単体では機能が限定される点にご留意ください。
予約状況確認や案内表示
受付にタブレットを設置し、現在の待ち時間や待ち人数をリアルタイムで表示することが可能です。待ち状況が可視化されることで、患者は自身の順番を把握しやすくなります。
また、診療案内や保険に関する情報などを表示するデジタルサイネージとしても活用できます。
これにより、患者の待ち時間におけるストレスを軽減すると同時に、有益な情報の提供にも役立ちます。
問診票の入力
タブレット用の問診システムを導入することで、患者は手書きではなくタッチ操作で問診票への入力が可能になります。電子カルテや予約システムと連携させれば、問診内容が即座に反映され、医師は診察前に詳細な情報の把握ができるため、迅速に診察できるでしょう。
電子カルテの入力や確認
タブレットは、電子カルテの確認・入力に最適です。
紙のカルテと比較すると持ち運びに便利で、その場ですぐに入力できるため、情報をリアルタイムで更新することもできます。
特に大規模な病院の場合、タブレットを導入することで各所への情報共有をスムーズに行えるでしょう。
ペーパーレス化を進められ、診察室や病室などにパソコンを持ち込む必要もありません。
診療時の説明
タブレットを使うと、診療時に画像や映像を用いての説明が可能となります。
レントゲン画像や検査データ、治療方法を説明する動画などを画面に表示することで、視覚的な情報を用いて具体的な内容を説明できるため、口頭だけの説明に比べて患者の理解が格段に深まります。
また、院内システムと連係することで、必要な資料をリアルタイムで表示でき、患者により詳細な情報を提供することも可能です。
業務指示の確認
タブレットは、スタッフ間の業務指示の確認にも役立ちます。
診察の進捗や検査結果といった情報をリアルタイムで共有できるため、次の処置の準備や引き継ぎがスムーズに行えます。
院内の業務フローがスムーズになれば、患者の待ち時間も短縮でき、ストレス軽減につながるでしょう。
また、電子カルテと連携させることで、検査結果やリハビリの実施記録なども共有可能でき、 ヒューマンエラーなどの防止も期待できます。
緊急対応時の情報共有
タブレットを導入すれば、緊急対応時の情報共有もスムーズに行えます。
従来は夜間や休日に患者の容体が急変した場合、担当医に電話で確認する必要がありました。
しかし、電話では状況が的確に伝わらず、対応の遅れにつながるリスクも少なくありませんでした。
タブレットを導入すれば、担当医は遠隔地からでも電子カルテの確認ができます。
担当医が病院へ駆けつけられない場合でも、現場のスタッフへ的確な指示を迅速に出せるため、緊急時対応の質が向上するでしょう。
在宅医療時の活用
在宅医療やオンライン診療の現場でも、タブレットは重要な役割を果たします。
ビデオ通話機能を活用すれば、訪問が困難な場合でも患者の表情や顔色を確認しながら診察を行えます。
また、訪問診療の際には、タブレットから院内の電子カルテにアクセスして情報をその場で記録・確認できるため、質の高い医療提供と業務の効率化を両立できます。
待ち時間や入院時の利用
患者向けのサービス向上ツールとしてもタブレットは活用できます。
たとえば、待合室に設置し、動画コンテンツや健康情報を提供することで、患者の待ち時間における満足度を高め、クレーム削減につなげることができます。
また、入院患者に対しては、タブレットで診療方針や診療スケジュール、検査結果の共有も可能です。タブレットを使用することで、入院患者に対しても手厚いサポートができ、患者の不安を和らげることができるでしょう。
病院でタブレットを導入するなら問診システムの検討もおすすめ

問診システムとは、タブレットを使用したデジタル形式の問診票記入システムです。
患者に入力してもらった情報は、システム内で管理して、電子カルテと結びつけられます。
紙の問診票の場合、後からスタッフがカルテに書き写す必要があるため、スタッフに負担がかかり人為的ミスが発生する点が課題となっていました。
デジタル形式の問診システムの導入により「問診業務」の大幅な効率化が可能です。
患者にも病院側にもメリットがあるため、病院システムのデジタル化にともない、問診システムの導入が進んでいます。
病院でタブレットを導入する際の注意点
病院でタブレットを導入する際は、注意点も理解しておきましょう。
注意点を理解せずに導入しようとすると、思わぬトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。
導入や運用にコストがかかる
タブレットの導入には、タブレット端末の購入費、システムの導入費などが初期費用として発生します。
また、端末代金を分割支払いやレンタルする場合は、ランニングコストとなるため注意が必要です。
利用するシステムによっては、月額利用料も発生するでしょう。
導入にあたっては、発生する費用と期待できる効果を精査し、費用対効果を慎重に見極めることが重要です。
タブレット操作に慣れていない人への配慮が必要になる
タブレットの導入にあたって、操作に不慣れな人に対してのサポート体制を構築しましょう。
高機能なタブレットを導入しても、スタッフが使いこなせなければ業務効率化にはつながりません。
また、スタッフに使い方を周知できていなければ、患者に操作をお願いする場面で使い方がわからないといったトラブルにつながる可能性があります。
特に高齢の患者の中には操作に戸惑う方も少なくありません。すべてをデジタル化するのではなく、必要に応じて従来の紙の問診票と併用するなど、利用者への配慮も重要です。
タブレット活用に合わせた業務フローを構築する
タブレットの導入効果を最大化するには、既存の業務フローの見直しが必須です。アナログな業務プロセスをそのままタブレットに置き換えるだけでは、かえって非効率になる恐れがあります。
「タブレットを使えば、どの業務を、どのように効率化できるか」という視点で、新しい業務フローを設計することが重要です。
必要な機能が搭載されているかの確認が必須
病院でタブレットを導入する際は、使用環境に合わせた機能の有無を確認しましょう。
業務上必要な機能がなければ、導入する意味がありません。
タブレットの導入時は、事前に「どのような機能が必要か」をリサーチしておきます。
必要な機能が確定したら、その機能が搭載されている端末やサービスの導入を検討しましょう。
患者やスタッフの利便性を考慮してタブレットの導入を検討しよう
病院でタブレットを導入すると、受付や問診票の入力のほか、業務指示や情報共有など、さまざまな用途に活用できます。
これによりスタッフの業務効率が向上し、患者のストレス軽減にもつながるでしょう。
ただし、導入や運用の際にはコストがかかります。
また、タブレットに慣れていない人が多い場合は、サポート体制が必要になるでしょう。
導入前にこれらのデメリットを知っておくことも大切です。
この記事で紹介したポイントをもとに、どのようにタブレットを活用できるのか、導入によるメリットが大きいのかを考慮しながら検討してみてはいかがでしょうか。
病院へのタブレット導入はコネクシオにご相談ください
病院へのタブレット導入は、コネクシオにお任せください。
コネクシオの「マネージドモバイルサービス」では、MDM運用代行を含めたモバイル端末の導入・運用・リプレイスなどを行っています。
導入に関する課題はもちろん、その後のサポートについても実施しているため、導入による運用負担を軽減可能です。
MDMではタブレットの一元管理も行えるため、セキュリティ面の対策にも対応しています。
病院へのタブレット導入を検討しているなら、コネクシオに一度お問い合わせください。